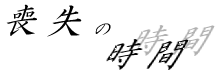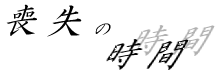馨子さま作
3 【病室のバレンタイン】
「佐伯さんたち帰ったの?」
「ああ、それより傷の具合は?痛みはないのか?」
「うん、大丈夫。ねえ、春海、あたし考えてみたら自分の身分を証明する物、今日はなにも持ってなかったと思うんだけど、どうして春海はあたしがここに運ばれたの、わかったの?」
「ああ。お前、手提げ袋の中に「春海へ」って書いた封筒入れてただろ、それでお前の持ってたアドレス帳から“春海”に該当する名前を探し出して、連絡をくれたってわけ。ったく、びっくりさせやがって。『頭から血を流して倒れていた』って連絡受けた時は、心臓が止まるかと思ったぜ。あんまり心配させるなよな。」
「うん、ごめん」
いるかは、小さくなって俯いた。
春海は、俯いたいるかの頬を両手で包むようにして、上を向かせた。
二人の瞳が交錯する。
いるかはそっと目を閉じた。
まだ青みの残る唇に、春海は自分の唇を重ねた。
「あっ」
「なんだよ? 突然」
「そういえば、あたしの荷物は?」
「ああ、なんだ。それならここにあるよ。」
春海はベッドの脇ある、入院患者用のロッカーを指差した。
「ごめん、春海、その中に小さい手提げ袋ない?花柄の。」
春海はロッカーを開け、中から花柄の小さな手提げ袋を取り出した。
「これのことか?」
「うん、それそれ。取ってくれる?」
「ほら。」
春海は、いるかにその手提げ袋を手渡す。
「ありがと」
受け取ったいるかは、中から着物の重ねのように紫紺と水色の和紙で包装され、金モールのリボンで飾られた小箱を取り出した。
『よかった、形はくずれてないみたい。』
いるかは、俯き加減で、その小箱を春海に差し出した。
「これ、バレンタインのチョコ。今年も作ってみたんだけど・・・・・」
後は消え入りそうな声だった。
「ああ、そうか、今日はバレンタインデーだったんだよな。この騒ぎですっかり忘れてたよ。ありがとう、開けていい?」
「あっ、うん。でも全然自信ないよ。あたしやっぱりこーゆーの苦手だし・・・・」
「なに言ってんだよ、去年のだってうまかったぜ。」
「んー、でも・・・」
そんなやりとりをしているうち、春海は器用にラッピングをほどき、小箱の蓋をあける。
「えっ、三色団子? ――――じゃない、これチョコレートなのか?」
それは、直径1.5センチ程の大きさのトリュフにしたスイートチョコ、ビターチョコ、ホワイトチョコ、抹茶チョコ、苺チョコを、彩りよく3つずつ黒もじ(菓子楊枝)にさしてあり、懐紙を敷いた小箱に収められたそのチョコレートは一見すると三色団子のように見える。
「和風っていうの? ちょっと変わってて面白いなと思って。」
「なんか可愛いな、コレ。食べるのがもったいないよ。お前、また腕上げたんじゃないのか?」
「へへへ・・・そうかな? でも味の方はわかんないよ。」
いるかはあくまでも自信なさ気に呟く。
春海は串刺しにされた団子、ではなくチョコレートを頬張る。
口の中にふわっ広がる紅茶の風味。
中国茶にも通じる少しオリエンタルな香りが鼻から抜ける。
「アールグレイか?」
「あ、スイートチョコのトリュフだね。うん、アールグレイの紅茶を混ぜ込んであるの。どうかな?」
少し不安気な様子で聞く。
「美味いよ。やっぱりお前、料理の腕あがってるって。」
そう言いながら、2段目の抹茶のトリュフを口に入れる。
「これも美味いな。中はホワイトチョコなのか?」
「うん、そう。ホワイトチョコのガナッシュを抹茶パウダーでくるんだの。」
「へぇ〜、チョコレートっていうと洋菓子のイメージしかなかったけど、和菓子っぽくもなるんだな。見た目だけじゃなく味もいけてるし。」
「そう? そう言ってもらえるとちょっと安心。実はね、今年は拍子抜けするくらいにスムーズに出来ちゃって、それがかえって心配で、心配で。なんか間違えてるんじゃないかって、ずーと不安だったの。」
『それって、やっぱり腕があがってるってことじゃないか・・・』
そんな変化に気づきもせず、しきりに首をかしげるこの小さな恋人に、春海はたまらなく愛おしさが胸に押し寄せる。
「自信もてよ。」
春海はそう言って、アールグレイと抹茶の香りが残る唇を近づけた。
ガラガラガラ
病室の扉が開き、病院には似つかわしくない格好をした男女が飛び込んできた。
「いるか!! 大丈夫?」
「いるか!! どうしたんだ、一体?」
「かーちゃん! とーちゃん!」
「もう、心配させて、あんたって子は! 春海君からの留守電きいて、すっとんで来たのよ。」
見れば、母、葵はワインレッドのカクテルドレス、父、鉄之介は蝶ネクタイのタキシード姿。
某国大使主催のパーティーから帰宅後、取るものもとりあえず、かけつけたのだろう。
「お二人が見えたら医師(せんせい)の方へと言われています。」
折角の甘いムードをぶち壊され、内心悔しい思いであったが、未来の義父母の手前、不機嫌な顔は微塵も見せず、春海は落ち着いた様子で、葵と鉄之介に話しかけた。
「ああ、春海君。いるかに付き添ってくれていたんだね、ありがとう。」
「いえ。じゃあ、医師(せんせい)の所までご案内します。いるか、ちょっと行って来るよ。」
「あ、うん」
春海は先にたって、廊下へ出た。
廊下に出ると、戸口のところに一人の男が立っていた。
見覚えのあるその顔に春海は「あっ、捜査1課の・・・」と呟いた。
「鹿島です。佐伯係長にいるかちゃんの警護を任されました。」
鹿島と名乗るその男は、そう言って春海たちに軽く会釈した。
「ありがとうございます。お世話かけます。」
春海は、佐伯のすばやい対応に感謝した。
「春海君、いるかの警護って何の事だね、事故じゃなかったのかい?」
鉄之介は不安気に訊ねる。
「はい、その事は道々ご説明します。」と鉄之介に答え、視線を鹿島に移すと「鹿島さん、すいません。ご両親を医師(せんせい)の所まで案内してきます。中、彼女一人になりますので、お願いできますか?」と頼んだ。
「ええ、もちろんです。それが任務ですからね。」
鹿島はにっこりと春海に笑いかけた。
道すがら、春海は事件のあらましを鉄之介と葵に説明した。
「じゃあ、いるかはその犯人にまた狙われると?」
「ええ、その可能性はあると思います。佐伯さん、あっ、佐伯さんというのは、警視庁捜査1課の警部さんで、前に里見であった事件を担当した方なんですが、その方もそれを心配して、だから鹿島さんをいるかの警護に回してくれたんです。」
「で、いるかはその事件の事を何と?」
「それが、記憶障害を起こしていて、覚えていないんです。詳しい病状についてはこれから医師(せんせい)に説明してもらいますが、そんな訳で、佐伯さんも今日のところは、事件について、いるかには何も話していないんです。」
「そうか・・・」
鉄之介は沈痛な面持ちで小さく唸った。
「おじさん、しばらくの間、僕を如月の家においていただけませんか?」
田辺医師の説明を受け、いるかの病室に戻る途中、春海は鉄之介に切り出した。
「そりゃあ、君がいるかの傍にいてくれるなら、これほど安心できることはないが・・・
しかし、徹君はどうするんだい?」
「あら、それなら徹君もうちに呼べばいいじゃない。」
それまで、二人の会話をだまって聞いていた葵は、事も無げにそう言った。
「ご迷惑でなければ、そうさせていただけるとありがたいんですが・・・」
「迷惑だなんて、全然。うれしいわぁ〜、息子がいっぺんに二人もできたみたいで。」
と少し華やいだ声を出した。
「お前、娘が大変な時に何を呑気な・・・・」
鉄之介は苦笑した。