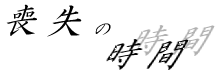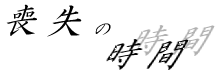馨子さま作
2 【喪失のペンダントヘッド】
いるかは、病室のベッドで眠っていた。
頭には包帯が巻かれている。
春海は、いるかの少し青みがかった唇にそっと自分の唇を重ねた。
唇にいるかの体温を感じ、少しだけ安堵の吐息を洩らした。
ふと、いるかの手元を見ると、何かを握っているのに気がついた。
そっと手を広げると、中から見覚えのある銀色の鎖。
去年のホワイトデーにプレゼントしたネックレスだ。
だが、それは何か強い力をうけたように途中で変形し、ちぎれている。
ペンダントヘッドのイルカもない。
『どうしてこんな・・・・』
眉根を寄せ、訝しげな表情でそれを手にしたとき、いるかが「・・・・うん」とくぐもった声を発し、うっすらと目を開けた。
「いるか、気が付いたか?」
「・・・・・・・・・・」
「いるか?」
「あなた、誰?」
「――――えっ?」
「逆行性健忘ですね。」
春海は、医師からいるかの症状についての説明を受けていた。
「逆行性健忘?」
「ええ、頭部外傷や縊死(いし)未遂、つまり首吊り未遂のことですね、その他一酸化中毒や尿毒症なんかで、意識障害を起こした後、意識が鮮明になった時に、その記憶障害を起こす前ことを思い出せない状態をいいます。記憶喪失の一種といったほうが分かりやすいかな。」
「ずっとあのままなのですか?」
「いえ、この方の場合は心因性の記憶障害ではなく、頭部打撲がその原因であると思われますので、体の回復とともに徐々に思い出してくると思いますよ。」
「そうですか・・・」
春海は少しホッとした表情で呟いた。
「あのー、お話中申し訳ございません。田辺先生、この患者さんのことで警察の方がおみえですが・・・」
「警察?」
春海と田辺と呼ばれたその医師は顔を見合わせた。
看護婦に案内され、二人の男が室内に入ってきた。
「失礼します。先程こちらに搬送された患者さんの事ですが・・・・」と言いかけ、すぐに驚いたような大きな声が上がった。
「は、春海? 春海じゃないか?」
「――えっ?」
突然、自分の名前を呼ばれ、春海は顔を上げた。
「さ、佐伯さん。それに可児さんまで。どうしたんですか、一体?」
「どうしたも、こうしたも。おい、ちょっと待てよ。お前がここにいるってことは、搬送された女性って、まさかいるかちゃんなのか?」
「ええ、いるかですけど・・・・」といいかけ、春海は何か気づいたようにハッとした表情を浮かべた。
「まさか、彼女の怪我に何か事件性があるんですか?」
佐伯、可児、この二人の男達は、警視庁捜査1課の刑事だ。
数ヶ月前、春海といるかの通う里見学習院で起こった殺人事件でその捜査を担当し、その時知り合った。 ( 『里見学習院殺人事件』参照 )
「実は、いるかちゃんが倒れてたというマンションの建築現場に男の刺殺死体があったんだよ。」
「刺殺死体!!それってどういうことですか?」
「順をおって説明しようか。若い女性が頭から血を流して倒れているという119番通報があったのは、今日の午後3時半ごろ。見つけたのは六段駅近くに住むご老人で、犬の散歩の途中見つけたらしい。あんまり犬が騒ぐんで半ば引きずられるようにあの現場にいったら、若い女性が倒れているのを見つけ、慌てて近所の民家に駆け込んで119番したとの事だ。」
「じゃあ、死体もその時発見されたんですね。」
「うん、まあ、ちょっと時間差はあるがね。最初、その老人は、置いてあった資材が死角となって死体には気づかなかったんだ。119番通報した後、救急車の案内をしようと現場に戻ったところ、死体を見つけて、また慌てて110番通報したというわけさ。」
「じゃあ、佐伯さんたちは現場検証を終えて、こちらへ?」
「ああ、“生きてるガイシャを最後に見た可能性のある女性” とくれば事情聴取せにゃならんからな。しっかし、その女性がいるかちゃんだなんて、本当に驚いたよ。」
「事情聴取ですか・・・・。でも、ちょっと難しいかもしれませんよ。」
「ちょっと難しいって、おいおい、お前、またおあずけ食らわす気か?」
「いえ、そういう訳ではないのですが・・・・・」
春海は、助けを求めるように、田辺医師を見た。
「如月いるかさんは、今、記憶障害を起こしているんですよ。」
田辺医師は、春海の視線に答えるかのように静かに言った。
「記憶障害?」
「ええ、記憶喪失の一種ですね。正式には逆行性健忘と言うんですが、頭部に大きな衝撃を受けたりするとですね、意識を取り戻した時、その記憶障害を起こす以前のことを思い出せなくなるんですよ。先程、一時的に意識を取り戻したんですが、こちらいる山本君のことを思い出せなかったんです。」
「春海の事をですか? じゃあ、事件の事も忘れている可能性があると?」
「ええ。ただ、今も山本君に説明していたところなんですが、こういったケースは体の回復とともに徐々に思い出すことがほとんどなんです。」
「そうですか・・・」幾分ホッした声音で佐伯は呟いた。
「失礼します。如月さんが意識をとりもどしました。」
看護婦が知らせに来た。
「そうか」
田辺医師と春海が同時に立ち上がった。
「我々も面会させていただけますか?」
「ええ、ただし相手が怪我人だということをくれぐれも忘れないで下さい。」
「分かりました。」
田辺医師、春海、少し遅れて佐伯、可児が病室に入った。
「あ、春海!」
「いるか!お前、俺がわかるのか?」
春海は、すぐにいるかの側にかけつけ、その顔を覗きこむように尋ねた。
「なに言ってんの? あたりまえじゃん。」
春海は、田辺医師を振り返る。
「記憶の錯乱でしょう。こういった時にはよくあるんですよ。」
「記憶の錯乱?」
いるかは眉根を寄せ、何が何だかわからないといった表情を見せたが、戸口付近に懐かしい顔を見つけ、大声で叫んだ。
「佐伯さん、それに可児さんまで。どーしたの、一体?」
「意識を取り戻したようだね、いるかちゃん。良かった、良かった。」
「意識を取り戻す? あーそういえば、あたし何でこんなトコにいるの? それにこの頭の包帯・・・」
「いるか、お前、頭から血を流して倒れているところを発見されたんだ。覚えてないのか?」
「頭から血?」
いるかは、頭に巻かれた包帯に手をやり、天井を仰ぎ見る。
「んー、そういえば、何か光る物が目の前を通ったんだよね、それで、“あっ”と思った次の瞬間頭にガツンって衝撃があって、目から火花ってよく言うけど、ホントそんな感じ。で、気づいたらココにいた。」
「じゃあ、その前後の事は覚えてないのか?」
「その前後? う〜ん、そういえば意識が遠のく時、何かやたら犬の鳴き声がしてた気がするけど・・・」
「いるかちゃんの倒れていたのは、六段駅近くのマンション建築現場。といってもまだ工事は始まってないんだけどね、そこに行ったことは覚えてるかい?」
今度は佐伯が質問した。
「あっ、近道。うん、そう、近道しようと思ったんだ。電車に乗り遅れちゃまずいと思って。」
「近道しようとその建築現場まで行ったんだね? そこで何があったか思い出せるかな?」
「う〜ん、誰か、誰かいたような気がする。でも、なんか頭の中に霧がかかっているみたいにおぼろげで・・・」
いるかはそう言って、手で頭をおさえるようにして苦渋の表情を浮かべた。
「ああ、いるかちゃん、無理はしなくていいよ。医師(せんせい)も言ってたけどね、体の回復と共に記憶も戻ってくるそうだから、慌てないでゆっくり考えて。」佐伯は優しくいるかに言った。
「じゃあ、今日のところはこれで。いるかちゃん、お大事に。また来るからね。」
佐伯はそう言って、可児刑事を伴って部屋を出て行こうとした。
「送ります」
春海は立ち上がり、佐伯たちの後を追った。
廊下に出たところで春海はおもむろに切り出した。
「佐伯さん、ひとつ心配事があるんです。状況から考えて、いるかは殺人の現場を目撃した為、襲われたんではないでしょうか? 犯人は犯行を目撃され、いるかをも殺すつもりで殴りかかった。ところが犬の声が聞こえ、人が近づいてくるのを察して、とどめをさせずに逃げた。とすると、また狙われる危険があるんじゃないかと・・・・」
「ああ、俺もそれを心配してるんだ。いるかちゃんの体のことを思って、今日のところは事件の事は本人には話さなかったんだが、とりあえず誰か警護の人間を回すよう手配するよ。」
「ありがとうございます。そうしていただけると心強いです。」
「ところで、いるかちゃん、さっき“何か光る物が目の前を通った”って言ってたけど、何のことだろうな。春海、お前わかるか?」
「多分、これじゃないかと・・・・」と言って、春海は着ていたジャケットのポケットから、いるかが握り締めていた銀の鎖を取り出した。
「鎖?」
「ええ、でも正確に言えば、この鎖の先についていたペンダントヘッドの事だと思います。これ、去年僕が彼女にあげたものなんですが、先にシルバーのイルカの飾りがついていたんです。でも、彼女はこの鎖だけを握り締めていました。この鎖自体も何か強い力が加わったように変形していますし、ヘッド部分のイルカもありませんでした。ですから、殴られた時に何かにひっかかって鎖が切れ、ヘッドの部分が飛んでいったんじゃないかと思うんです。」
「じゃあ“何か光る物”っていうのが、そのイルカの飾りだったってわけか、なるほど・・・」
少し考えるような素振りをした佐伯は、隣にいる可児刑事に向かって訊いた。
「おい、可児、鑑識さんから何か聞いてないか?」
「いえ、鑑識さんからはそのような物が見つかったという報告は受けていません。」
「そうですか・・・」
春海は、小さなため息を漏らした。
「ところで、いるかちゃんの両親の姿がなかったけど、また海外にでも出張なのかい?」
「いえ、今日はどこかの大使主催のパーティーに出席とかで夫婦で出かけたと聞いてます。さっき自宅に電話したんですが誰も出なくて、一応留守電に入れてはあるんですが・・・」
「そうか、確かいるかちゃんの父親って外交官だったよな。お嬢様ってわけだ。」
「そうは見えないですけどね。」
春海は苦笑交じりに答える。
「まあ、取り澄ましたお嬢さんより、断然いるかちゃんの方が魅力的だよ。お前だってそこに惚れてるんだろ?」
「ええ、その通りですよ。」
春海は臆面もなくそう答えた。
佐伯は、幾分揶揄するつもりで言ったのだが、春海の即答に逆に赤面する羽目となった。
『ほんのガキの時に本当の相手にめぐり逢える、そんなこともあるんだな。』
なにか眩しいものを見るように、佐伯は春海の端正な横顔を見つめた。
「で、春海、お前これからどうするんだ?」
「とりあえず、ご両親が来るまでここにいるつもりです。」
「でも、お前んとこ、弟がいるんじゃなかったか? まだ小学生だろ、大丈夫なのか?」
「ええ、今日は友達のところにいるはずですから。その友達の兄が僕の友人なんです。あ、そうそう、佐伯さんも知ってるはずですよ、東条巧巳。彼の妹と僕の弟は同じ学校に通ってて、友達同士なんですよ。さっき巧巳に電話して頼んでおきましたので、その点は心配ありません。」
「そうか、ならいいんだが。じゃあ何かあったらすぐに連絡してくれ。」
「ええ、わかりました。」
春海は軽く会釈して、佐伯たちを見送った。